僕は生きるためにスパゲティーを茹でつづけ、スパゲティーを茹でるために生きつづけた。
スパゲティーの年に
私はこの作品を初めて読んだ時、なぜなのかわからないけれどこの一文に胸を打たれました。この人の本を読まなくてはならない。そう思いました。
そして作品を読み進め、登場したこの部分。
スパゲティーたちはおそろしく狡猾だったから、僕は彼らから目を離すわけにはいかなかった。
スパゲティーの年に
もはや美学なんだ。そう思いました。現実でありながら、そして比喩的でありながら、これはどうにも別世界なのだ。しかもこの本に事実としてある。実態を持つ。そういうものしかここには出ていないのだから。
そしてこの一文。
夜もまたひそやかにスパゲティーたちを待ち受けていたのだ。
スパゲティーの年に
もう言葉にもならない、胸の収縮。恋をしていた青年期のような、そんな気持ち。
最後の❇︎の後の文章は胸を昂らせる言葉ばかりが使われています。これほどまでに短い文章にここまでロマンチックを詰め込めたらそれは素敵なことでしょう。
私はそんな一つに芸術を感じてやまないのです。
「解釈」
このまま話として受け止めても良いくらい言葉が素敵でそこから想起される全てが美しいのですが、やはり何か言いたいことが隠れている気がするのです。
そもそも彼にとっての「1971年」と「スパゲティー」とは何なのでしょう。最後の一文を見るとその謎の一部は解けます。
1971年に自分たちが輸出していたものが「孤独」だったと知ったら、イタリア人はおそらく仰天したことだろう。
スパゲティーの年に
この輸出していたものとは「デュラム・セモリナ」です。つまり「スパゲティー」。
つまり「生きるためにスパゲティーを茹でスパゲティーを茹でるために生きた」僕は「生きるために孤独を煮詰めて孤独を煮詰めるために生きた」のです。
ではその孤独を煮詰めるとはいったいどのような作業であるのかということも問題になります。
孤独を煮詰めるというのはつまり、孤独を見つめそれを管理し、ある意味それに抱かれながら生きるということではないのでしょうか。
だから僕がスパゲティーを茹でる(孤独を煮詰める)部屋に、誰一人として入ってこなかったのではないでしょうか。つまり彼の今に思い出であれ外界の物事であれそういう多くのものが入らなかったというわけです。
あまりにその孤独との対峙を極め過ぎていたからです。スパゲティーのことしか見つめていないし、ある意味ではスパゲティーのことをかいかぶり過ぎ、そしてスパゲティーを深く想い過ぎていたのです。
つまり僕は「孤独」に見舞われそれに付き合っているうちに自分の方から孤独と二人きりになろうとしていた。孤独と合わさったままでいようとしたのでしょう。
しかしそこでいよいよ孤独に飲み込まれるという時〔死んだ蝿のようになっている時〕電話がかかってきます。
その電話で僕の孤独は解けたようにも思います。それはきっと僕の「スパゲティーライフ」の終焉とも言える大イベントであったからこの少ない文章の中で電話のシーンがなかなか多かったのでしょう。
まとめ
この素敵な文章をこれからもきっとふと思い出せば読むだろうと思います。ひとまず今思うことを書きましたが、また別のタイミングで読んだら変化することもあるかもしれません。
その時はまた記事を書けたらと思います。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました!
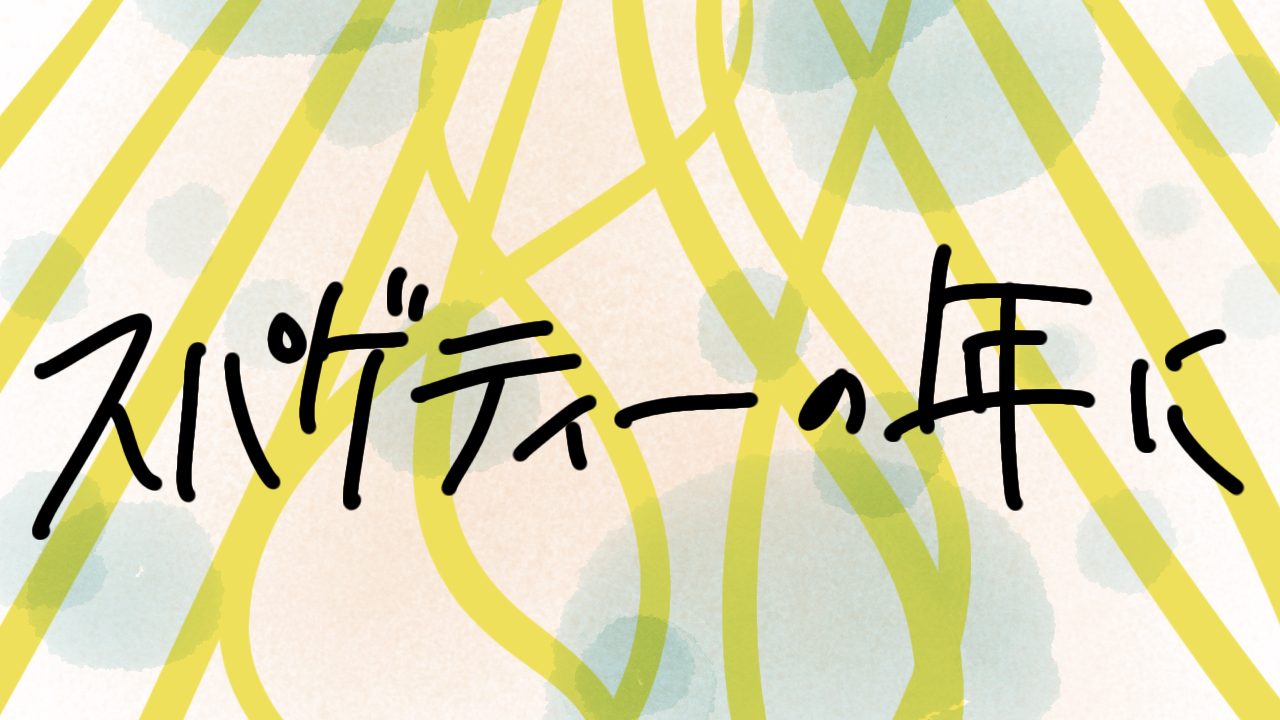


コメント