はじめに
久しぶりに作品をあげてみようと思います。
二千字程度のとっても短いショートショートです!お時間があれば読んでみてください。
薄暗い、恋愛ものを書いたつもりですが、もしよろしければ読んでみて感想をTwitter等で教えてください!
ここではブログの形式上横文字になってしまいますので、縦書きで読みたいという方は、こちらに貼っておきますPDFをダウンロードして読んでみてください。
ショートショート『ベッドで哲学なんて』本文
もう何分が経ったのだろうか。ずっと私は躊躇ったまま君の頭を撫でるばかりだ。ティッシュペーパーをくしゃくしゃに丸めて床に放ると君はいつも私の身体に体重をかけて匂いを嗅いだりキスをしたりする。すべてを記憶にする儀式をするみたいで、それは丁寧で厳かだ。私はそんな君の儀式の贄として君の頭を撫でながら、君が噛みちぎった小さな袋のことを考える。私の頬に落ちた君の汗のゆくえについて考える。思い出せば何度だって恋をすることができる。君がどこかへ消えてしまったとしても、それは変わらないだろう。
消える。君はいかにもふと消えてしまいそうだ。それくらい、私の人生のなかでは珍しく、君はたしかな希望だった。それはある種禍々しいほどぼんやりとしたあたたかな灯りだった。そういう美しいものが存在し続けるなんて嘘みたいだ。美しいものが美しいままで在り続けることはもっと嘘みたいだ。それならいっそ、と思う。記憶のなかでのみ、美しいものが美しく在れるのだということを認めてしまいたい。そして君を、私の儀式の贄にしたい。私はそういう儀式をするためのちからをまだ持っていない。私はおそらく、もっと俗世的に君を愛している。
だから私は君に触れられるとき、いつも無機物みたいだ。君に触れられると私の身体は奇妙に美しく青白く光って見える。美しく在ることに、囚われている。それは気持ちの良いことだ。肉体、と思っても、心のなかにそれが在るのだといつも思える。それを忘れたくはない。けれど君は、心で肉体を認めてそれを操っているみたいに見える。その意味で君はいつも自由だった。それでいて自分を肉体に閉じ込めているふうでもあった。君は自由がこわいことだと知っていた。そのことは、薄暗い部屋で私の目をじっと見るあの光のない瞳を見ればすぐにわかる。私はその恐れを捉えきれないけれど、それでも君を刹那的にでも慰めてあげたかった。それで私はいつも奥歯を噛んで目を閉じた。私のなにもかもを使っても届かないところに君はいつも取り残されているみたいな顔をするから、それがいつもつらかった。私はなんにも知らない子どもみたいな女であるような気がして、もっともっと自分を苦しめたくて君を愛した。愛すれば愛するほど、私の前提にある忌むべき秩序は静かに解けていくような気がした。そしていつかこの解けた秩序の糸が、どこか遠くのほうに取り残された君に届いて欲しいと願っている。
君の肩を撫でると、君はこの狭い部屋の空気を揺らして幽かに笑った。そして私の胸の辺りに唇をあてた。
「ちょっと痛いかもよ」
そんなことを言っておいて君の愛情にはいつも迷いがないから、参ってしまう。この狭苦しいベッドの上で何度も何度も殺されかけては蘇生されるうちに、私にはだんだん覚悟みたいなものができていく。空気の揺れや、君の瞳の光り加減とか、生きているとか、死の影とか、時間の連続性とか、そんなものがわかっていく。それで眠って、朝になって君とコーヒーを飲んで笑い合えば、またすべて忘れて、平気で洗濯機のボタンを押したり髪を解かしたりするのだから不思議なものだ。
君のひととおりの儀式が終わる前に、と私は思う。君の髪の毛をあと五回撫でたら言ってみようかなと考える。衝動的に聞こえる言葉を、こんなふうに吐くのはおかしいかもしれないけれど、私の弱さに免じて許して欲しいなんて甘えてみる。
一、二、三、四、五。
君の顔の骨を右手で触って私の顔のほうに誘い出す。君は私の唇を指で触って小首をかしげる。
「ずっと一緒にいようね」
ばかみたいなことを一生懸命言ってみてから、前に私自身が君に「できない約束はしないで」と言ったことがあるのを思い出した。でも君は少しの間の後、うん、とたしかに言って私の首のあたりに収まった。君の髪から、私のシャンプーの匂いがした。君の肩の向こうにカーテンの隙間の青い光が見える。私はいったいどこへいってしまうのだろう、と思う。少しこわくなって目を閉じると、君の体温にふと気づく。流れてくる熱を分け合って、同じ濃度になるみたいで、それが私にまどろみの気配をもたらしていく。私の熱が、君にも流れていくように少し強く抱きしめてみた。青い光が薄くなっていく。光は薄く薄くのびて私の部屋に流れ込んで止まない。君はしきりに私の頭を抱きしめて髪を撫でている。さらさら。さらさら。熱が流れて、それもまたこの部屋に絶えず流れ、溶けていく。
ベッドで哲学なんてするものじゃないね。
そんなものは、思ったことを言って、言ってしまって夜が明けてから一人でコーヒーでも飲みながらするものだ。
そう思ったら、君の体温がどれだけあたたかいものか、やっとわかったような気がした。
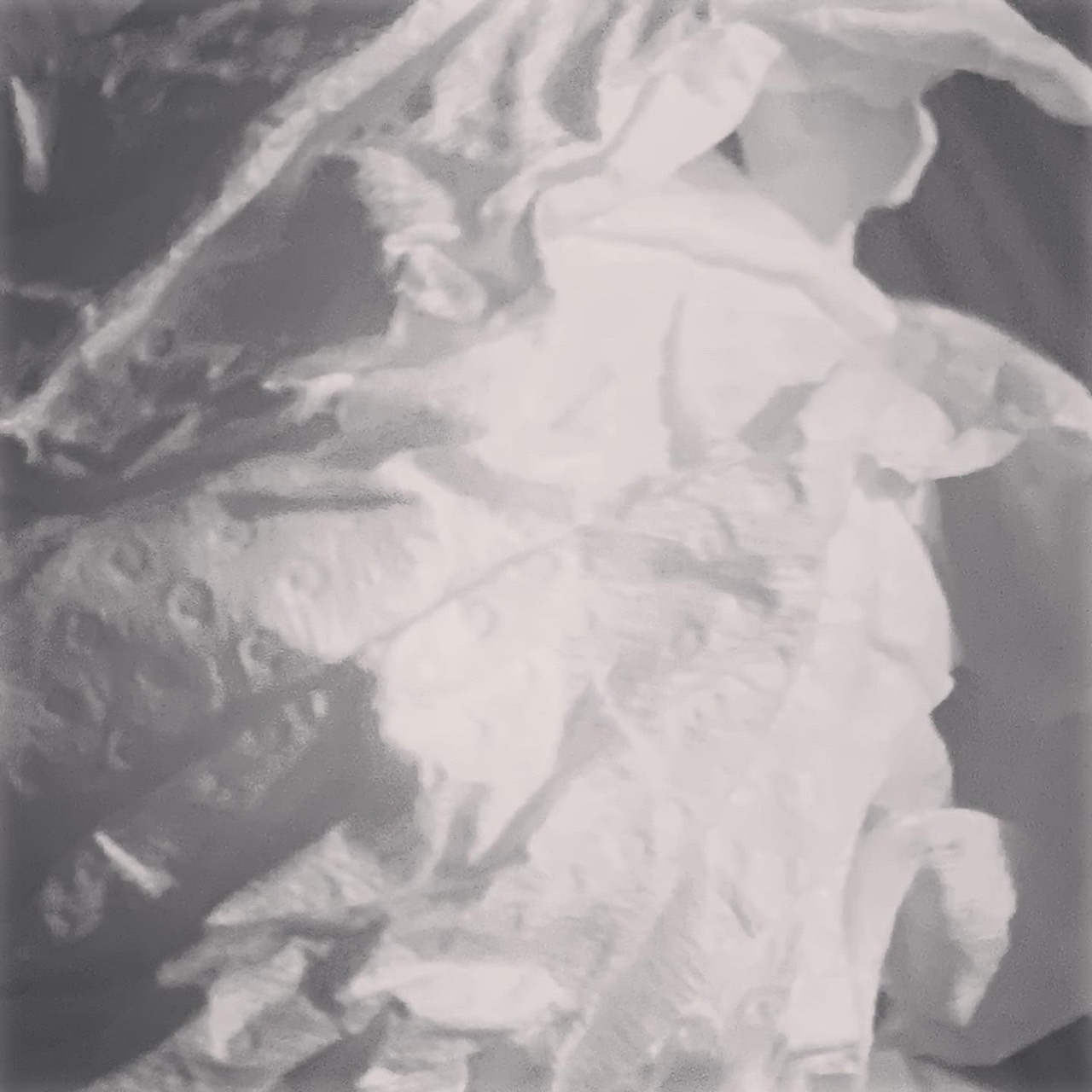


コメント