はじめに
前回の記事では「さようならギャングたち」の全体を通した書評と、彼の表現についての見解を、「解説」の部分で言われていたことなども元にしながら綴ってみました。
その記事のリンクを下に貼っておきます。
今回からは第一部、第二部、第三部それぞれの詳しい内容を書いた記事をアップしておこうと思います。そしてその「第一部」の回として今回の記事を書いていこうと思います。
「さようなら、ギャングたち」第一部をめぐって。
高橋源一郎氏はこの作品の第一部と第二部について、「躰」で書いたのだ、ということをおっしゃっています。
つまり、監獄、失語症などの彼の背景を通して(この話については先程貼り付けたリンク先の記事に書いたので割愛させていただきます)湧き上がった感情をあえてコントロールしたり体系化させたりせずに、絶望のもと、力の限り書いているという印象を受けました。
しかし、しっかりとした小説としての体裁は整えられており、その中でそれこそ蛇行している文章を蛇行極まりない構成の中で書き連ねられているのです。
それゆえになのか、私としてはこの第一部はロマンチックの塊のような章とも言えるのではないかというふうにも思えます。なんといっても、「舞台設定」と「悲しみ」これを同じくらいのレベルで極限まで表現し切れることがもう感心に値すると思う。
私自身も小説を書くので、私個人としてはそのことに関してすごく彼を評価することができます。というのは、「舞台設定」と「悲しみ」は全く素質が異なるように思えるにもかかわらず、彼はそれらを同じようなテイストでかきあげるからです。
「舞台設定」はロマンチックにそして独自性を出しつつ描いていくのがものすごく難しい部分です。それを、「昔々、人々はみんな名前を持っていた」から始まり、その名前が自分でつけるものから、恋人がつけるものへと変わっていったということが言われ、そこに効果的に独特なセックスが入ってくる。だからこれがロマンチックなものになりうるわけです。
Ⅰ「ありがとう」の章をもう一度読んでみてほしい。洒落てはいない、でも俗らしくもない。なんというか、高橋源一郎的セックスなのか「さようならギャングたち」的セックスなのか……。
村上春樹の小説にもセックスが多くは感傷的に洒落た雰囲気を纏いつつ出てきますが、この作品の著者のそれはもっと棘があって非現実なのです。だからこそそれがアクセントになり、この舞台設定におけるファクターの一つとなっていくというわけなのです。
しかしそれにしても、この高橋源一郎的セックスなのか「さようならギャングたち」的セックスなのかわからないような独特なセックスを描いていると思いきや、Ⅲ「キスして」の章ではなかなかにロマンチックなそれが繰り広げられているのです。
「ベットの中で謎解きをしないでね」なんてS・Bのセリフはなかなか好きです。
ここまで「舞台設定」について少々話しましたが、「悲しみ」とは逆にロマンチックに描くことが限りなく許された感情の動きです。だからそれを描く時にはいかに悲しくするかといういちベクトルにその方向性が定められてしまいそうですが、この作品においてはそれが本当に軽やかに、しかしそれでいて重く深く伝わるのです。
私は「悲しみ」が好きですが、好きゆえに自分なら悲しみまでの場づくりを入念に行い、存分に悲しみを描いてしまうと思うのです。
しかし高橋源一郎氏の「悲しみ」の描き方はとてもソフトで、さりげなく、でも深い、リアリティ溢れるものであるのです。
例えば娘キャラウェイに赤いリボンをつけて一緒に出かけ、遊園地に入る時はただになるシーンや、キャラウェイが男の子たちとキャッチボールをして、その後「わたし」と言葉を交わすシーン。
「ダディ!」
「なに?キャラウェイ」
「キャラウェイ、手を握られちゃったよ、男の子に」
「もてるなあ、キャラウェイは」
「そんなことないけどさ」
ここなんかはどうしようもなく切ない。私の言葉が拙いために、うまく言えないけれど本当にとても悲しみを上手に描いていると思うのです。
同じように、「死」と「展望」や「愛」なんかを組み合わせていく悲しみの描きかたは既存のものとしてあるのでしょうが、そこに込める具体的な流れが至極素朴で切なさを煽るものとなっているのだろうと思われるわけです。
また、このキャラウェイがあまり取り乱さない性格なだけに、とても悲しみの質が上がっていると言えるのだろうと思います。
もちろん高橋源一郎氏がこの「第一部」を「解説」にて書かれているように自らの人生として描いているのかもしれませんし、その上でなにか気持ちの吐露をする場として使ったのではないかとも思えるわけです。
先程の悲しみの質というのは、そういうある種の感情の必然性、本物の絶望感のもとで描かれた非常に稀有なそして輝く性質を持っていると思えるのです。
Ⅳ 「うんち」について
本当は「ん」が反転しているのですが、私のパソコンではそのように打ち込めなかったゆえ、このように書いています。
この章の、「わたし」が家計簿に「うんち」と書いてしまうところが非常に好きで、これはなかなか素晴らしい表現であり心理描写であると思ったのです。
詩や言葉を綴るとき、こういう心境になることは容易く理解できるけれど書いてみようと意外とできないことであるわけです。
「あひるのおまる」を讃える詩を書きたいと思ってぶるぶる震えながら色々と思考し「うんち」としか書けないというアイロニー。そしてそういう詩人としての現実。
そういうものが実にリアルに表されています。
私はこのような飾り気なく、それでいて感情という棘が張り巡らされていて、そのうえでとても的確で素敵な表現がとても好きです。
まとめ
今回もなかなかの長さになってしまい、すみません。
続けて次回からも「第二部」「第三部」の記事を上げていこうと思います。
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました!
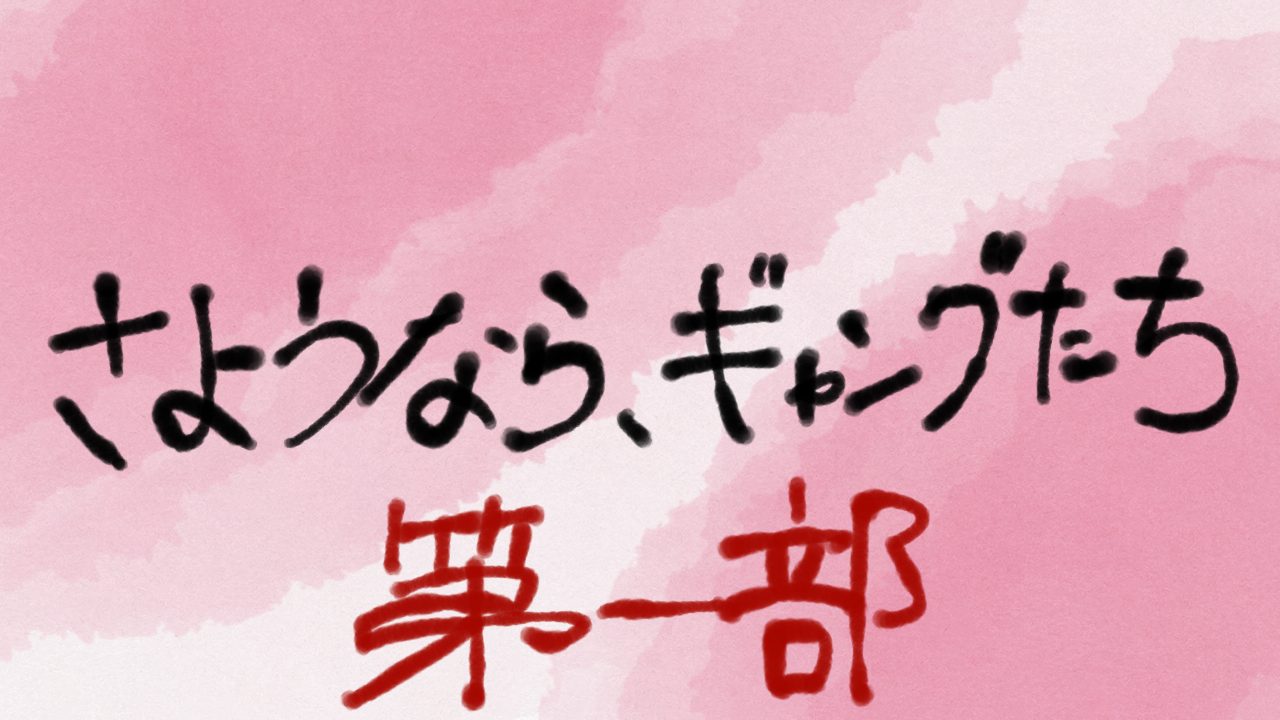



コメント