オーダー内容
「砂漠に1匹のカエルがいた。あるとき彼は旅に出ることに決めた。砂漠を越え、野を越え、山を越え、辿り着いたのは深海。そこで彼の生涯で最も衝撃的な出会いをする。」というあらすじを私自身の身近な方から頂戴し、各種描写を入れつつ細かい設定も私の方で考案し、これを物語化いたしました。
因みにこちらは7700字です。
あらすじをいただく場合はキーワードをいただく場合に比べて物語自体が長くなりがちですのでその点ご容赦ください。( ´ ▽ ` )
物語
「西の彼方に」
地球の果て、具体的にはどこかなんてわからない、そんな場所に一匹のカエルがいた。強いていえばそこは砂漠だった。しかしカエルにとってはその名称などどうでも良いことであったし、国や地名なんて概念は尚更彼の興味から遠いところにあった。彼がただ抱えていたのは少しの苦しみを伴う渇きと、底知れぬ悲しみ、その二つだ。彼は小さな草を噛み砕いてその汁を吸い、どうにか渇きに耐えつつ、干からびてしまうのを待っていた。今年の乾季は最悪だった。いつもなら完全に水がなくなることなどない場所さえ乾いてしまったのだ。砂漠に住むものたちは皆、太陽がお怒りだと騒いだ。たくさんいた彼の仲間はみんな死んだ。家族も死んだ。最愛の女の子も死んだ。彼にはなにも残らなかった。なにも残してくれないくせに彼の命だけは残ることになった。そんなものはいらなかった。いらないと嘆きながら彼は毎日草を噛み続けた。やがて徐々に雨が土を濡らすようになった。カエルは死にたいのになぜかその雨水を飲んだ。そうしているうちに、カエルはいつの間にか身体的に死からだいぶ離れたところに来てしまったようであった。それに反して死に近い心を抱えたまま少しずつ池のようになっていく水たまりに浮かんでいた。
「……ですか。」
カエルの名前を呼ぶ誰かがいる。しかしその名前と思われる部分だけ変に異国めいていて、それがどのような名前なのかよくわからない。でもそれが彼の名前であると、なぜか彼には直感的にわかった。見上げると、そこにいたのは象だった。名前は知らない。
「はじめまして、どうして僕の名前を?」
カエルは尋ねる。
「おや、その名前で正解でしたか。なんとなく、そんな名前のような気がしたものですから呼んでみただけなのですがね。」
カエルは引きつった笑顔を象に向けた。象は朗らかに笑っていた。
「あなたには仲間はいないのですか?」
と、象。
「いないよ。みんな乾いて死んじまったさ。君にも仲間はいないようだね。」
象の笑みはまだ崩れていない。
「わたしはある禁忌を侵しました。それで群れから追放されたのです。とはいえここではわたしのような脆弱でそれでいて大きいものなど、一人ではとても生きていけないでしょう。」
「君は、仲間に謝罪でもして群れに戻った方がいいんじゃないか?」
「そういうことではないのですよ。君にもわかるはずです。生きるということが必ずしも最も有用とは限らないということを。」
カエルは自分にもその心境について心当たりがあったので、なにも言わずに水の上に浮かんで象のことを見上げていた。
「あなたは、伝説などという類のものを信じますか?というより、そういうものを信じてまで生きていく必要があると思いますか。」
「難しい質問だな。どんなものかによるとも思う。」
象の浮かべる笑みはどこか不敵なものに変わっていた。
「知りたいですか。」
「まあ。」
「いいでしょう、教えます。わたしが抵触してしまった禁忌とは、これにまつわるものです。この世界の真理と、”再会”にまつわる伝説。」
カエルは唾を飲んで、象の話に耳を傾けた。象の話はおおよそこのようなものであった。まず世界とは何なのか。それは我々が触れる範囲にある、「全て」のことであるという。つまりその上にある、触れることはできないけれど存在するというものに関しては「世界」も含んだもっと大きな括りに分類されるということらしい。因みにとりわけその「世界」には様々な不可思議なものごとが存在している。物質的なものから形而上的なものまでその幅は実に広い。その強いていえば後者のほうのうちの一つに、「再会の伝説」というものがある。象はこれに相当な興味を抱いた。しかし象の世界には、「形而上的なものごとを信じてはいけない。」という掟があり、皆がこの世界は砂漠でできていて、それ以外の要素は持たないと教えられていた。しかし象は初めてその話を何かの拍子に小耳に挟んでしまって以来、「世界」が持つ全ての要素を信じてしまったし、「世界」が砂漠でできていることすら信じられなくなってしまった。それを群れの中の最も信用していた者に打ち明けたところ、その仲間に裏切られ、たちまち群れから離脱させられたというわけだ。
「でもどうして君たちはそんなに形のないものを否定するんだい?」
「知りませんが強いていえば伝統のようなものです。まったくくだらないことですよね。でもきっとその方が都合が良いのでしょうね。楽になるのですよ、群れの秩序を保つことが。」
「なるほど。それでその再会の伝説というのは何なんだ?」
象はまた語った。本当の愛を知っている者は死んでしまうとき、自分にとって最愛の相手に会うことができるのだという。それがどんなに離れた場所にいたとしてもだ。「本当の愛」が実のところ何なのか、詳しいことはわからない。それでも自分の愛が「本当の愛」であると思うのなら、その定義を聞いたとしても、それ以上の愛を用意することは不可能だろう。だからそこは気にしなくて良い。象はそのようなことを言いながら優しく笑っていた。
「しかしね、それを達成するためにはいくつか条件があるのですよ。因みにあなたは今あなたのいるこの場所が”世界”で最も美しい場所であると信じますか?」
「いや、そうは思えないな。」
「であるならばあなたは砂漠を出なくてはなりません。そして旅をするのです。行ける範囲で構わないから、逆に行けるところまで行くのです。そして世界で最も美しいと思える場所にたどり着いた時、そこであなたはあなたの生を打ち切ります。そこにはもちろん運も必要です。まずこの外の世界が美しいのかそうでないのかもわかりませんし、それにそのようなものごとには神秘的な力のようなものも必要だと言いますからね。」
カエルは考えた。もう彼には失うものもない。唯一残されたのは命くらいだ。その命さえ、今ここで尽きてしまうのを待っている。実際そんな風に時間を使っているくらいならいっそのこと旅にでも出た方が良いのかもしれない。
「旅に出るのも良いかもしれない。しかし君はここを出ようと思わないのか?僕と一緒に出てみないか?」
「いや、わたしは行く気ないです。ここ以上に美しい場所があることは信じていますが、わたしには愛が欠落している。実際仲間がいなくなってしまってもあなたのように打ち拉がれませんし、あなたのように恋人もいませんでした。だからそのようなところで死んでも結局は同じことなのです。それに外の世界が思ったよりも美しくなかったらわたしは悲しい気持ちになります。だからここにいた方が良いのです。ずっとその麗しさを信じていられるから。」
「そうか……。ところでどういう風にしてここを出れば良いのだ?」
「ふむ。ここを北に行くのが一番早いでしょうね。しかしある場所を越えるとライオンが出現するエリアに入ってしまいますから、その先は共に進むことはできません。わたしはあなたのように小柄ですばしっこくはないのですから。しかしそこまでは一緒に進んで差し上げましょう。」
「ありがとう。背中に乗っても良いかい?」
「どうぞ。」
カエルと象は三日ほど砂漠を北に歩いた。その間、これまでの人生やこの世界のことについて語り合った。彼ら以外には誰もいなかった。カエルは象のこれからが気になった。しかしなぜだかそれを聞くことはできなかった。
三日後、早朝に象と別れる場所に辿り着いた。
「どうもありがとう。君と会うことはないと思うけれど、またあったらよろしく頼むよ。」
「いいえ。どうか気をつけて。最も美しいと思うところで自分の生を打ち切るのですよ。」
「わかっているさ。君も気をつけて。」
カエルは砂を蹴って走った。カエルだけ、少しの涙を瞳に浮かべていた。
カエルがそこから北に行く途中、ライオンには一度も会わなかった。みたこともない芋虫には遭遇したので、それを食べたり、いつかのように草を噛みながら先を急いだ。彼は何日進み続けたのかわからないほど長い時間をかけて北に進んだ。何度も橙の日が沈んで、闇が広がり、白い光が差した。彼は漸く砂漠の果てに街を見つけた。ヒトが営む、小さくて寂れた街だ。彼はそこでレタスを齧っていた。棚の上のたくさんのレタスの中の一枚だ。すると少女が棚の前にやってきた。少女は何か意味のわからぬことを店のヒトに言う。すると店のヒトは彼を袋に入れて少女に渡した。彼は自分の人生を振り返って悲しみと後悔の念に駆られた。少女は家に着くと、カエルを袋から取り出し、なにやらとても大きな水槽に入れた。すると後ろの方からしゅるると細い音がする。振り返るとそこには蛇だ。彼は思い切って蛇の頭に乗った。彼の足は震えていた。
「お願いだ、食わないでくれ。」
カエルは懇願した。
「なぜだ。」
蛇はそう答えた。
「食われたくないからだ。」
「なぜだ。」
「死にたくないんだ。」
「なぜだ。」
「心残りがあるんだ。」
「何だ言ってみろ。」
カエルはこれまでの経緯を全て、慎重に嘘偽りなく話した。蛇は落ち着いてそれを聞いていた。
「つまりお前というカエルはわざと生かされたのかもしれんな。」
「つまり僕は自分に本当の愛が備わっているのか確かめなくてはならない。」
カエルは言った。
「愛か。素敵だな。」
蛇は渋い声でそう言った。
「俺なんか愛なんぞとは無関係な質さ。まったく最近のミラといったら俺の世話が行き届いていないし、たまに持ってきた餌がこれとは、酷いものだ。」
ミラとはあの少女のことらしい。蛇は悲しそうだった。
「おいカエル、お前は早くここを出るんだ。この水槽を出る助けはしてやる。そのあとはそこの窓から出ろ。」
カエルは礼を言ってミラの家を出た。そしてまた北にひたすら走った。今度は数えて六日目に大きな森にはいることになった。そこは湿度が高く、カエルである彼にとっては最適の環境であったが、どうにもそこは彼の思う最も美しいであろう場所とは違う。しかし彼が生きる上では素晴らしい環境であることは間違い無かったのでそこで少し休息をとった。そして彼は芋虫を食べながら彼を今まで支えた家族や、この冒険を支えてくれた象や蛇を想った。そして彼らはカエルにとって恩人であることは間違い無いのに、誰ひとりとして満足な愛を知らなかったし、幸せな死に方をするとは到底思えないことに気がついた。カエルはそのことを思ってこの「世界」の不条理を嘆いた。嘆きつつ、何の罪もない芋虫をたくさん食べた。その次の朝、彼はまた歩き始めた。森には勾配があり、徐々に山に向かって行った。あるいはすでにここは山なのかもしれないが、彼には詳しいことはわからなかった。少し歩いたとろでカエルは小さくてほとんど流れのない、濁った川を見つけたのでそこで顔を洗って水を飲み、葉っぱを食した。目の前でザリガニが共食いに向けた争いを繰り広げていた。一匹のザリガニが、争いを傍観するカエルに気づいて一瞬目を奪われたそのとき、そのザリガニは命を落とした。カエルは他人の死に介入してしまったことを深く悔み、川をあとにした。
自分や世界について思考を巡らせながら、長い長い山道をただ登った。時々、もうすでに自分は死んでいるのでは無いかとも思ったし、永劫の時が流れる場所に吸い込まれてしまったのかもしれないとも思った。そのくらい長い間、彼は山を登っていた。彼が頂上についた頃にはもう季節も移ろい始めた頃合いで、辺りを埋め尽くす木々もどこか侘しさを含む趣を纏うようになった。カエルはそんな山の中をただ煢然たる心持ちで進んだ。彼はどこまでも北に進む決意をしたのだ。もしかしたら西か東にずれているかもしれないが、なにはともあれ南には戻っていない。確実に、カエルにとって「みたことのある世界」は増えていた。しかし、山頂を少しすぎると彼は突然死をすぐそばに感じた。いつぶりだろう。砂漠にいた時以来かもしれない。彼は倒れ込んだ。腐った葉とともに自分は土になってしまうのだろう。カエルは覚悟して、寝転んだまま空を仰いだ。群青色の、寂寞たる雰囲気さえ連れた空だ。彼の意識は空に吸い込まれそうに朦朧とし、走馬灯のように様々なことが思い出された。最後に現れたのは彼のかつての恋人だった。彼女はなにも言わずに笑っていた。そして遠くに流れていく。どこかもわからぬ暗闇の果てに吸い込まれたのだ。どうして?彼も同じ場所に行くはずなのに、どうしてか彼女は離れていったのだ。怖くて瞼を閉じていられずに、現実を見ようと目を見開いた。白い光がさす。おそらくは朝なのだ。しかし、何だか白夜の日のような不自然さがある。本来あるべきものが無視されているような、そういう何かが混在した奇妙な感覚だ。そんな空気に包まれたカエルの前に開けた山に、なにやら光の塊のようなものが現れた。光と言えば実体がなさそうに思うが、この塊には実体がある。石のようなものを軸に持っていて、そこに光を纏っているようにも見える。とにかくそのようなものに出会った。しかしカエルは彼自身も驚くくらい、その事実を難なく受け入れることができた。
「私は森の神秘を守る者だ。」
光の塊の発した言葉であるということは理解できる。しかしこれは声ではなかった。空気の振動による伝達ではない。心に、頭に直接届けられた、ある種電波のような言葉たちだった。それを理解した頃、光の塊はまた言葉を発し始めた。
「大地を離れようとも、冷静に、美を美として見ることを忘れず、光のないところでも本来光があるであろう所を見ようとせよ。さすれば、おまえの旅、その人生、果たされるだろう。」
カエルはなにも言えなかった。
「ここを下ったのち、西に進みなさい。なにがあろうとも、そこがどこであろうともひたすら西に進みなさい。お前にとっての世界で一番美しいものとは、そこにあるだろう。」
カエルはそれでもなにも言えなかった。カエルがただ頷くと、光の塊はどこかへいってしまった。もう姿は見えない。
カエルはただひたすら山を下った。季節が変わり、寒空が広がろうとも、ただひたすらに山を下りた。降りた先には草原が広がっていた。彼はその草原を西に進んだ。どこまでもどこまでも歩いた。カエルはここで、自分はもう砂漠には一生帰れない。そのことを真に悟った。どこか寂しい気もした。進まなくても僕の末路は制限されていたし、旅に出る選択をしても、人生の可能性は消えていく。そこに沈殿するようにして突然存在感を増した生にまつわるアイロニーが、彼の心を潰すように押し続けていた。それが催す吐き気に耐えながら、彼は止まることなく歩き続けた。カエルの体にとっては大きすぎる負荷がかかったが、なぜか途中で雷が鳴ろうが竜巻が起ころうが、それらはわざと彼を避けるようにして起こったので彼はおよそ安全に進むことができた。おそらく何か、あらゆるものを超越した力が彼の周りの状況をそうさせたのだろう。彼は西に進むにつれて、この世界に起こりうるすべての物事を信じられる支度が整い始めた。草原は、いつの間にか丘をつくり、そこを越えた先には大きな川を携えた森があった。川はやがて北の方へ向かって行ったが、カエルは迷わず真っ直ぐ西へと進んだ。その間なぜか如何なる動物とも会わなかった。配置されたように、必要な時に食糧として必要な虫や水はあったが、襲われることはなかったのだ。彼が西へ進むうちに数回季節が回った。あまりに寒い時は枯れ葉に潜って眠ったりもしたし、あまりに暑い時は休んで水を飲むことにのみ従事したりもした。そうしているうちに、砂漠にいた頃に比べ、カエルは幾分歳を取った。歩くペースは落ち、食べられる量も減った。傾いた夕陽のように、彼は未来に向けたその絢爛たる眼差しは持ちながらも確実に歳を取っていった。彼はそれを自覚した日、朝、進むべき方向に、知らない香りを感じた。粘着質な風に乗った、鼻をつんとつく匂い。彼はその匂いのする方に走った。そこにはまさにコバルトブルーの鮮やかな、きらびやかな、彼の知らない場所があった。不規則に揺れるその表面は、優しく光を反射して彼を誘う。彼はその光景に故郷の影を見出し、望郷の念に駆られた。その心は彼を動かす力となり、その力に導かれた彼はその青い砂漠へ走って行った。その周辺に着くと、彼の住んでいた砂漠のような場所が広がり、そこに転がる星の砂は彼の足を小さく切り裂いた。しかし彼はそのようなことは気にも止めず、ただ走った。そして漸く青い砂漠の入り口についた時、カエルの頭上に大きな鳥が現れた。白くて大きな鳥だ。鳥はカエルをくちばしで挟み、空高く飛び上がった。白くて大きな鳥は一言も喋らなかった。ただ淡々と彼を何処かへ持っていくために、青い砂漠の上を飛んだ。西へ西へ飛んだ。ベタつく風がカエルに張り付いては流れた。青い砂漠を眺めているうちに、それはどうも水であるらしいということがわかった。飛魚が飛んで、水しぶきをあげたからだ。水色だったそれはあるところで突然深い、深い色に変わった。底は見えなくなった。鳥は、飛び始めて何分か経った頃、重々しく声を出した。
「お前の目指す西の果てとは本当に存在するのだろうか。」
「どういうことだ。」
「空を飛んでいると、西の果てなんてところは結局のところないのでは無いかという気がしてならないんだよ。」
カエルはぼんやり海を見ていた。
「この辺なのだろうか。私はお前を西の果ての海に届けろと言われたんだ。」
「誰に?」
「何となく聞こえてきたんだ。物理的にじゃなくて、何となく感覚的にね。」
その後彼はしばらく飛んだ。カエルの意識はなぜか少し遠のき始めた。眠いのか、終わりなのか、それはよくわからないがとにかく意識が流れていくのだ。
音も遠のき、すべての動きがスローになる。
彼が目を覚ました時、そこは水の中だった。深く深く沈んでいく最中だ。何か勢いよく叩きつけられるようにして水に入ってしまったのだ。たとえば、空高くから落とされるとか。
彼は下ばかり見つめ、どこまでも現れぬ水の底を探していた。しかし彼はそこで森で聞いた言葉を思い出し、光が本来あるべき場所を見た。それは真上だ。太陽がある場所。そこからのぞく太陽の光は海の水を光らせ、一辺倒な青にグラデーションを持たせていた。そこに彼の視界の端から一匹の魚が現れ、少しの泡沫を生んだ。そこにさらなる陽の光が差し込み、反射する。泡沫の表面は緑や赤の色彩も発しながら、優しくそして宗教的な輝きを放ち、様々な青を滲ませる海の調和を実に可憐に乱していた。カエルはそんな美しさに見惚れながら、海の底へと沈んでいった。ついにその輝きも見えなくなり、光が僅かにしか届かなくなった時、彼は海の底にたどり着いていた。そこにはわずかな岩のみが存在していて、あとは何の乱れもない、まさに秩序そのものという感じがした。そして最も驚いたことといえば、彼自身の呼吸が完全に保たれていたことであった。乱れなく、正確に、リズムを刻んでいた。間違いなく、彼以外の何かからもたらされた効果だ。彼はそこでまたも、光のあるべき方向を見た。彼の頭上だ。そこからは先ほどまで、細々とした光のみが漏れていたにも関わらず、今はどうだろう。尋常では無い光が差し込んでいたのだ。太陽が水面すれすれのところまで近づいてしまっているのでは無いかと思うほどの光の量だ。それはあの日彼が山で見た光を彷彿とさせる光景であった。するとその光の中に影が現れた。彼はたじろぎつつ、その光に目を奪われていた。
「誰か……いる?」
彼は思わず呟いた。すると空気も水も震わせない類の、所謂どこかオカルトチックな声が聞こえてきた。
「私よ。」
彼は考えた。何しろ物理的な声では無いから、それがどのような声なのかわからないのだ。
「誰だ。」
「忘れたの?」
光は群青の中で静かに揺れ動く。
「かなしいわ。」
「かなしい?」
「あなたを愛していたから。」
彼の中に衝撃が走った。喜び、悲しみ、その感情の方向こそ違えど、程度はあの間伐の時と似ていた。ああ、この青に溶ける光のモーションが一番、世界で一番美しい、きっとそうだ、違いない。
彼は光に浮かぶ影を掴みに行こうと、海底の砂を蹴る。何か大きな力が彼にかかって彼を押し上げる。彼は彼女を呼んだ。彼女は当時と寸分違わぬ美しい姿で現れ、彼の手を引いた。そして彼女は彼の名前を呼んだ。彼女は彼の最も愛した人だった。かつてあの砂漠で、彼は彼女に恋をしたわけだ。
「ここでずっと待っていたの?」
「ええ、あなたをね。」
「どうして砂漠じゃダメだったのかい。」
「それではあなたが簡単に私に逢えてしまうからよ。」
「何だそれ。」
彼は笑った。彼女も笑った。二人は深海を、光を探してどこまでも進んだ。どこまでも、どこまでも。

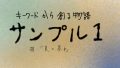

コメント